- HOME
- 糖尿病と循環器疾患
糖尿病と循環器疾患の関係
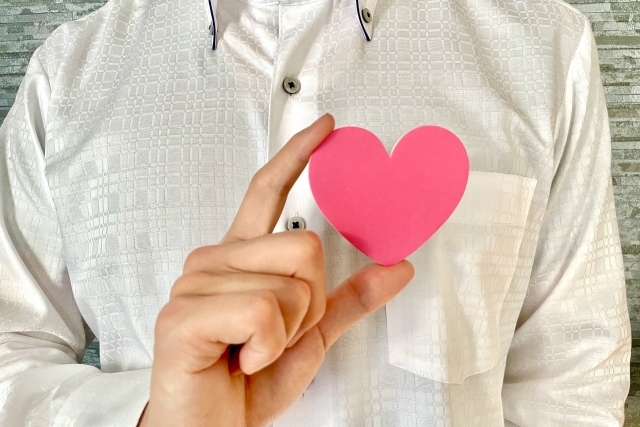
循環器は、血液などの体液を体に循環させる機関の総称であり、心臓・動脈・静脈・毛細血管・リンパ管が該当します。糖尿病による高血糖状態の持続は、血管に大きな負担をかけて動脈硬化を促進させ、正常な血流を妨げて全身に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。このため、糖尿病と循環器疾患は密接な関係にあるといえ、しばしば両者は互いに影響し合います。
糖尿病の治療に際しては、血糖コントロールだけでなく、循環器の異常にも注意する必要があります。逆に言えば、糖尿病の治療を適切に行うことで、循環器疾患も未然に防げる可能性があるのです。
糖尿病と循環器疾患の共通の危険因子
糖尿病(とくに2型糖尿病)と循環器疾患は、共に生活習慣の影響を大きく受けます。両方共通の危険因子としては以下が挙げられます。仮に糖尿病や循環器疾患と指摘されていなくても、リスクになる生活習慣は早めに改善することをおすすめします。
- 不健康な食生活(栄養バランスの偏り、不規則な食事)
- 運動不足
- 肥満
- 喫煙
- 過度な飲酒
- ストレス など
糖尿病と関連する循環器疾患(例)
動脈硬化
動脈硬化は、動脈壁が肥厚・硬化し、弾力性を失う状態です。「血管が脆くなった状態」と言えるでしょう。糖尿病は動脈硬化の主要なリスク因子の一つであり、高血糖状態が持続すると、血管の内壁が傷つき、コレステロールなどの脂質が血管壁に沈着しやすくなります。さらに、糖尿病に伴う血液の酸化や炎症反応は動脈硬化の進行を加速させてしまいます。
心筋梗塞
心筋梗塞は、心臓に血液を送る冠動脈の閉塞により心筋が壊死する疾患です。高血糖状態による動脈硬化によってリスクが生じるので、糖尿病患者は健康な方よりも心筋梗塞のリスクが高いと言えます。また、糖尿病に伴う神経障害により、心筋梗塞の典型的な胸痛を感じにくくなる「無痛性心筋梗塞」のリスクも高まります。
狭心症
狭心症は、心臓の冠動脈の狭窄により、一時的に心筋への血流が不足した状態です。糖尿病患者は狭心症のリスクが高いのですが、明確な症状が現れにくいのが特徴です。高血糖状態による動脈硬化や、糖尿病に伴う脂質代謝異常が、冠動脈の狭窄を加速させます。適切な血糖コントロールが狭心症の予防と管理に重要です。
心不全
心不全は、心臓のポンプ機能が低下し、体に必要な血液を十分に送り出せない状態です。高血糖状態が心筋細胞を直接障害することに加え、冠動脈疾患や高血圧症の合併が心不全のリスクを高めます。また、糖尿病治療薬の一部に心不全のリスクを高めるものがありますので、糖尿病治療中の方も注意が必要です。
高血圧
高血圧は、持続的に血圧が高い状態を指します。原因となる生活習慣が共通していますので、糖尿病患者さんの多くに高血圧症との合併が見られます。糖尿病による血管の柔軟性低下や腎機能障害が高血圧を引き起こし、逆に高血圧が糖尿病の合併症を悪化させるという悪循環を生みます。両疾患のバランスを考慮した、的確な血糖・血圧コントロールが重要です。
甲状腺疾患
甲状腺疾患(甲状腺機能低下症など)は、糖尿病によって発症リスクが高まることが知られています。両者は自己免疫疾患としての共通点があり、糖尿病(とくに1型)患者では甲状腺自己抗体が陽性になりやすい傾向にあります。また、甲状腺機能の異常は血糖コントロールに影響を与えるため、糖尿病患者さんには定期的な甲状腺機能検査をおすすめいたします。
